外国人材雇用のデメリットが許せて、活用を考えたい!と考えているけれども、「どこに相談したらいい?」「何から始めたらいい?」を解説します。
外国人材の雇用の流れ
- Step1採用戦略・人材要件を決める
在留資格のところで触れましたが、どのような活動(仕事)内容を外国人材に担ってもらうかで人材探しや求人方法が異なってきます。この部分は、外部ではできないため、社内で十分に検討する必要があります。必要に応じて、経営者だけでなく、受入部門の責任者や一緒に働くチームメンバーなども交えて検討するのがオススメです。(受入をスムーズにする目的です。)
どのような能力や経験が必要かMUSTとWANTを整理すること、求める日本語能力(話す・聞く・書く・読む)についても決めておきましょう。
- Step2行政書士に相談
上記の活動(仕事)内容、外国人材が行うことができるのか、またどのような在留資格になるのかを確認しておきましょう。
- Step3求人を出す
外国人材は、「外国人を採用しているかな?」と、一般的な求人からは応募をためらうこともあります。そのため、外国人材向けの求人や、一般求人では「外国籍の方も応募可能」や「外国籍の社員も活躍してます」と記載することで、外国人の自分も応募していいんだ!と思ってもらえ、応募が来ます。実際に私もこの記載をしたら外国人材からの応募が増えました。労働基準法に抵触するので、間違っても国籍を書かないようにしてくださいね。
- Step4選考
1で決めた人材要件にどれだけあっているかを選考を通して確認しましょう。書類だけでは非常にわかりにくと思うので、できる限り面接(直接会うまたはオンライン)を行うのがベターです。
- Step5内定
良い人材と出会えたらいよいよ入社に向けた準備をしましょう。内定通知や雇用条件通知書などは日本人と同様に準備をしましょう。この際に、「雇用は在留資格の取得が前提である旨」記載をしましょう。
- Step6在留資格の取得
種類にもよりますが、在留資格取得には書類の準備も含め2〜3ヶ月はかかります。できるだけ早く取り掛かりましょう。
- Step7入社
在留資格が取得できれば晴れて入社となります。
雇用の目的に合った人材探し・求人方法
公的機関や学校へ直接アプローチすることで費用を抑えて求人する方法を紹介します。
厚労省「外国人雇用サービスセンター」
東京・名古屋・大阪・福岡には、厚生労働省の機関である「外国人雇用サービスセンター」があり、外国籍の人材に対しては、就職(転職)活動の支援(仕事探しや面接方法など)を、受入企業に対しては、求人の出し方や就職フェアなどの支援をしています。
学生の夏休み中のインターンシップ支援も行っており、「外国人材を雇用してみたいけど、受入できるかな?」「実際に雇用するにあたってどんな準備をしなければいけないんだろう?」「実際にどのような仕事を任せられるか?」 などの疑問を持つ企業はインターンシップを利用してみるのも良いかもしれませんね。
留学生が多い大学や専門学校へ直接求人を出す
独立行政法人日本学生支援機構が実施している「外国人留学生在籍状況調査」結果や、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団「留学生受け入れ専門学校名簿」などが活用できます。
外国人材に限った話しではありませんが、学校の就職支援課に「留学生を採用したい」と申し出ることで求人の仕方や学校によっては授業や就職支援の時間に企業紹介の機会をもらえることもあります。
日本貿易振興機構(JETRO)「高度外国人材関心企業情報(OFPリスト)」
高度外国人材(在留資格でいうと、「技術・人文知識・国際業務」、「研究」、「経営・管理」、「法律・会計業務」が該当)のみが対象ですが、無料で外国人材に自社をPRすることができるページを掲載することができます。
その他民間企業でも外国人材の採用支援を得意としているところもあるのでまた紹介しますね。


困ったときの相談窓口
困ったときは、公的な相談機関を活用しましょう。
在留資格の種類ごとで相談窓口が異なりますので以下を参考にしてください。
在留資格「特定技能」に関すること▶出入国在留管理庁
在留資格「技能実習」に関すること▶外国人技能実習機構
在留資格「高度外国人材」に関すること▶日本貿易振興機構(JETRO)
在留資格「定住者」に関すること▶外国人雇用サービスセンター
行政書士の探し方▶行政書士会
今回は以上となります
1と2をまだ読まれていな方は、ぜひ1と2もご覧ください
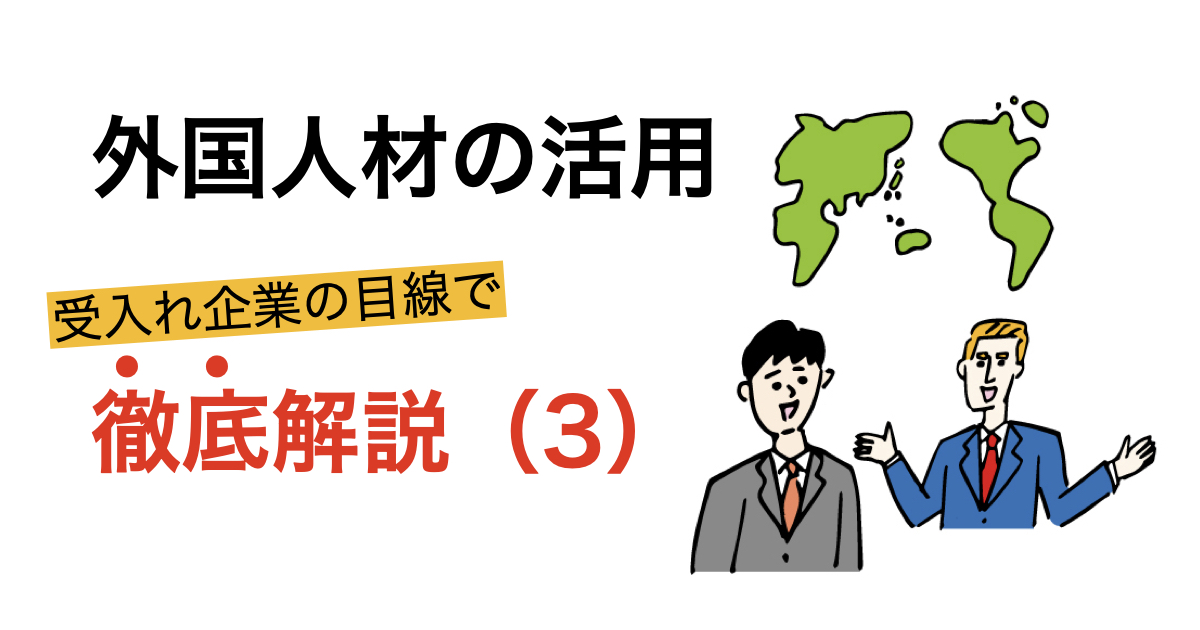
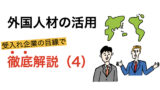

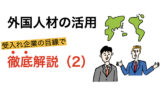
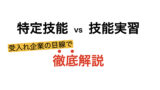
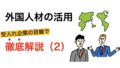

コメント